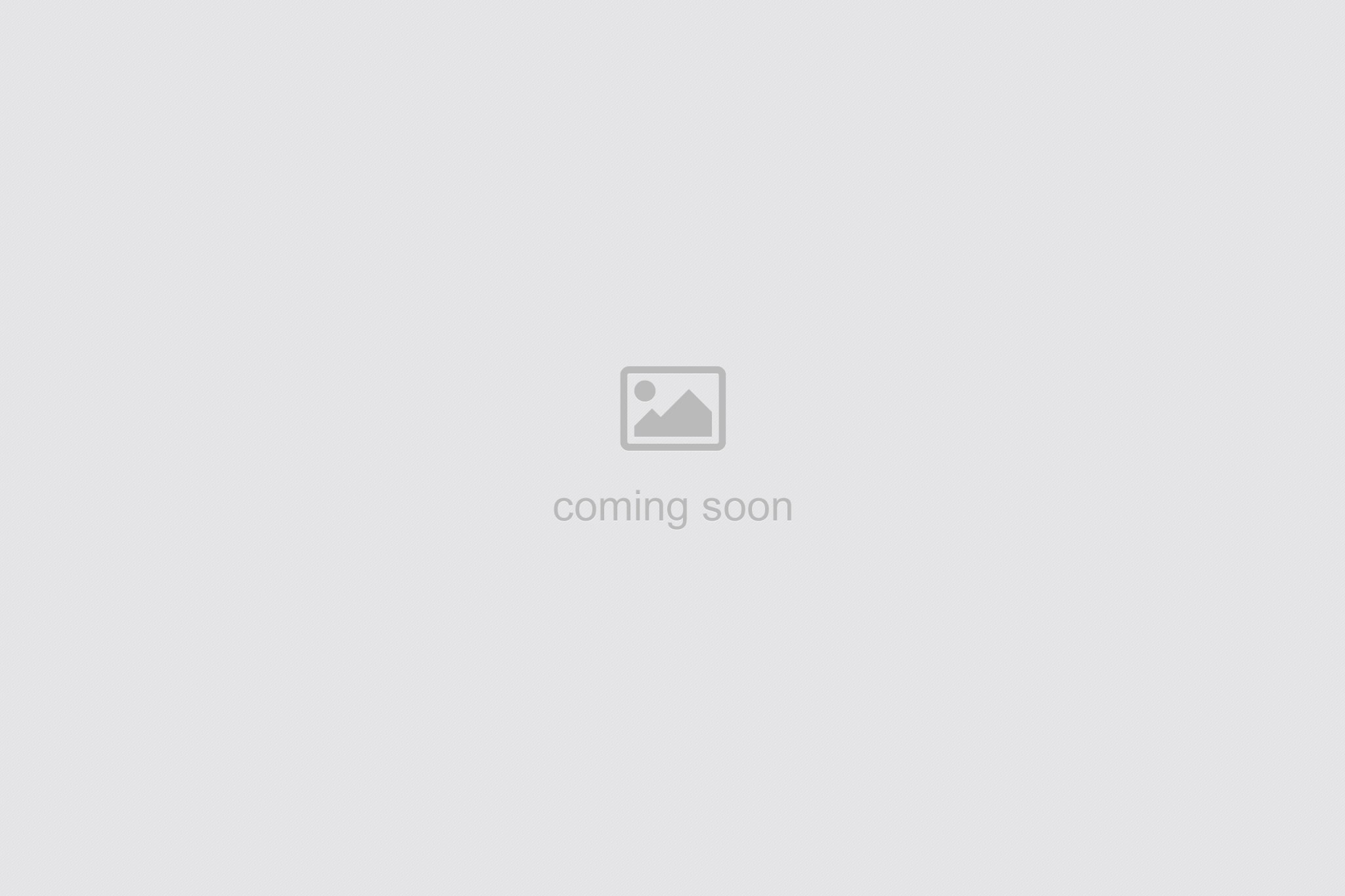megomego 2018
過去のすくすく通信(2018)
子どもの発達~安全感の輪~
2019-03-01
《 こどもの発達~安全感の輪~ 》
いよいよ今年度も残すところ1か月となりました。
子ども達にとって、また、保護者の皆様にとっては、どのような1年だったでしょうか?
身の回りの始末を一人でサッとできるようになったり、小さい子におもちゃを貸してあげたりとグンと成長した面と、『友達とのちょっとしたケンカが多くって』や、『いろいろな所に行ってしまうので目が離せなくって』などちょっと困った行動に捉えられる面も・・。しかし、このような行動も視点を変えると、また違った捉え方ができます。少し前に一人で遊ぶことが多かった子にとっては『友達とのちょっとしたケンカ』は友達に興味を持つという一歩進んだ姿となりますし、『いろいろな所を探索』できるのは、なにか怖い事や不安な事があった時に戻れば抱きしめてくれたり、安心させてくれたりする特定の大人(保護者の方や保育者)がいるからと言えますよね。
このように赤ちゃんの頃から、保護者(園では保育者)に不安を受け止めてもらい安心感を得て、また外の世界に出ていろいろなものに触れたり、好奇心にかられながら遊んだりする中でいろいろなことを学んでいきます。
このような、不安→特定の大人とくっつく→安心感→外の世界へ→不安 は、『安全感の輪』と呼ばれており、この体験を積み重ねていくことで、少しずつ特定の大人から離れる時間や空間を長く、広くしていきます。
子どもが安心感を持って外の世界にいるとき、特定の大人は子どもを信頼して見守ることが大切です。怪我をさせないようにと先回りして必要以上に手を掛けたりすると、子どもはなかなか離れられなくなったり、体験する機会を失ってしまいます。一方、不安になって特定の大人を求めている時には、しっかりと受け止めて安心してもらうことが大切です。その時々の子どもの発達や状況に応じて大人は見守りや応援をしたり、受け止めやなぐさめてあげたりと臨機応変にかかわることが健やかな心身の発達のカギになると言われています。
ついつい、すぐに手を貸したり、少しでも危険なことを防ぎたくなったりしてしまいがちですが、いずれ自立して広い社会にでていく子ども達が困らないように、いろいろな体験を小さいころから積み重ねて、困った時に乗り越える沢山の方法を獲得できるように見守ることはその子を信じることでもありますよね。
もうすぐ春。期待と不安を胸に新しい環境に飛び込む子ども達を私たち大人が見守り、応援し、もしもくじけそうになった時はちゃんと受け止めてあげたいですね。(著:江良)
参考図書 遠藤利彦(2017)赤ちゃんの発達とアタッチメント/ひとなる書房
兄弟ケンカの仲裁
2019-02-01
行事や集会の時などに、各クラスの子ども達が遊戯室に入ってくると、兄弟を見つけ、手を振ったりアイコンタクトなどでお互いを確認し合う姿が見られます。
上の子は、『ちゃんとみんなと上手に移動できてるかな?しっかりお話聞けてるかな・・』など心配な眼差しで見つめていて、下の子は『しっかりやってるよ~!見て~エライでしょ~!』といった無言の会話や合図が交わされているのでしょうか。見ていてほのぼのします(*’ω’*)
園ではこんなに仲良し兄弟なのに、お家ではケンカが激しくておもちゃの取り合いばかりで困っている・・・や、ケンカの仲裁もどうしたら・・・など保護者の方からのお話を耳にします。場所が変わるだけで子ども達の心にどんな変化があるのでしょう。
子ども達にとって兄弟は、一番身近な小集団で、そこで身に付けた人との関係づくりや社会性を、園の友達や周囲の大人たちとの関係性の中で発展させながら磨いていくのではないでしょうか。乳幼児期の子ども達のケンカには、これからの人間関係を築くための土台となる要素も含まれてくるので、ケンカの仲裁に入る親の言葉掛けは重要ですよね。
しかし、子ども達は言葉ではまだうまく伝えられずイライラや心のモヤモヤを体で表現しがちです。
それを大人が暴力で解決すると、それが正しい解決の仕方だと子どもは認識してしまうだろうし・・・。
とことん取っ組み合いをする兄弟ケンカは、手加減を学べず、相手が友達でもやり合うだろうし・・・。
大人が一方的に「ケンカはやめなさい!」「ごめんなさいしなさい!」だけで一喝して済ませる手段では、この先成長した子どもにとって、解決し合う手掛かりや方法が乏しくなってしまいますよね。もちろん危険な行為や危ないと感じたときは、未然に防ぐことも必要です。しかし、心のモヤモヤに対しては、まずは子どもの気持ちを知ろうとすることを優先させてあげるのはどうでしょう。『こういう理由なんだよね』と思いを代弁してあげると『あっ、わかってくれてるんだな』と心を許し、信頼した相手に想いを吐き出せるのかもしれません。その後で、善悪の判断をじっくり伝えてあげた方が子どもにとってはスッと、入っていきやすいのかもしれません。
親の言葉や周りの大人がケンカの解決へ導いてくれた言葉は、大人になった時に自分の気持ちを上手にコントロールする為のヒントにも繋がっていきます。また、友達とケンカしたときの解決策の選択肢の一つになったりします。
実は、日頃子どもに掛けている親の言葉には、この子には将来どんな大人になってほしいか。どんな兄弟関係を築いてほしいか。と願いを込めながら伝えている言葉が多かったりします。『友達には優しくね。』『ウソは良くないよ。』など・・・子どもの心の成長を期待しながら、日々子育てに奮闘している親の気持ちを知ってか知らずか、次の日にはケロッ!(^o^)と仲直りしている兄弟ちゃん達。家を一歩出るとちゃっかり仲良し兄弟に変身してたりするんですよね・・・(*’ω’*)(著:園長)
小さな店員さん
2018-11-01
先日、“子育て支援 mego mego マルシェ ”が行われました。
おそろいの制服を着た年長の店員さんが
「いらっしゃいませ~」 「こちらはいかがですか?」 とそれぞれのコーナーから元気に声を掛けていました。
子ども達はこの日を楽しみにし、だいぶ前から時間をかけて準備をしてきました。
紙をくるくる巻いて作ったハート型のオブジェや夢のお守りとされるドリームキャッチャーを作ったり、
どのように接するとお客様が喜んでくれるかなどを『こども会議』で話し合ったり、
実際にシミュレーションをしてきました。
当日の開店前は、店員さんという初めての体験に
『ドキドキする』『上手くできなかったらどうしよう・・』と期待と不安が入り混じっているようでした。
しかし、はにかみながら声を掛けていた子ども達も、時間が経つにつれ自信がでてきたのか
積極的に自分のおすすめの品物を伝えるなど、短時間の中でぐんぐんと変化をみせ、
一人ひとりがイキイキとした姿で接客をしていました。
マルシェを終えて感想を聞くと
「疲れた~。でも、面白かった~!」
「ありがとうって言ってもらって嬉しかった♥」
と味わったことのない達成感があったようです。
日常の生活の中で、どちらかといえば何かをしてもらうことが多い子ども達が、
今回は店員さんとして相手を思って行動し、感謝されるという体験を通して、
自分は誰かのために役立っているという気持ちが湧き、働く意欲や楽しさを味わうことができたのではないかと思います。
この感情は自己有用感と言われ、集団の一員としての社会性が身に付くとともに、自分は価値のある人間だということを理解する「自尊感情」を高めることにもつながっていきます。
自己有用感が高い子は積極性や思いやりがあり、人と関わりをもつことが好きになるようです。
マルシェ終了後にエプロン姿でじゃれあっている小さな店員さん達を見ながら、
人と関わるのが大好きな子ども達が、これからも人との関わりをどんどん広げていき、
地域の一員という思いが芽生えてくれたらいいなぁ・・・と微笑ましく眺めていました。 (著:江良)
~トンボから学ぶこと~
2018-10-01
トンボのメガネは~♪”の歌が各クラスから聞こえてすっかり秋の気配が感じられ、子ども達にとっては、バッタやトンボなど虫取りを楽しめる時期となりましたね。先日ひばり組さんでは、トンボをめぐり子ども達の大論争がありました。
トンボを採るのが上手なA君。園庭でつかまえたトンボを家に持ち帰りたいと主張しますが、なかなか採れない他の子達は『ダメだよ!すぐ逃がしてあげた方がいい!だってかわいそうでしょ』と主張。毎年ひばり組さんではこのような光景を見かけます。今年はどんな流れになるのか。しばらく様子を見守ることに・・・。数日後、他の子達もトンボ採りの腕前が上達し、二人、三人とトンボを持ち帰る子が増えてきました。するとトンボを持ち帰りたいと主張する意見が増えていき・・。またまた、数日すると、持ち帰っても家の人に逃がしてあげなさいと言われるとの声も。さぁトンボをめぐる大論争がいよいよ暗礁に乗り上げてしまいました。 一連の子ども達の心の動きを見守っていたクラスの先生がタイミングを見て「子ども会議を開こうか!」とみんなに提案。自分たちが経験したことから意見を出し合い、最初のA君の気持ちと同様の思いを感じながら、どうしたら家に持ち帰れるかを話し合いました。
こども会議から出た答えは、「自分用の虫かごを作り持ち帰ろう!その後、どうするかはお家の人とお話しして約束を守ろう!」でした。
早速、空のペットボトルを家から持ってきて、自分専用の虫かご作りをしていました。その日から、子ども達はトンボ採りに専念し、捕まえたトンボをじーっくり観察し、目大きい!口の中こうなってるの!ワッうんちするんだ!など発見がいっぱい。加えて、草を入れてあげよう!強くハネ持てば痛がるよ!など労わる気持ちも伺え・・・。中には「このトンボ赤いから夕焼け見たんだよ♪」なんてメンコイ声も(*^_^*)
土と草を虫かごに詰め、空気が必要だからとフタに穴をポチポチ開けたり、トンボが休める細い木を入れてあげるなど、トンボが住みやすいように虫かごの中の小さな世界を大切に考える子ども達。そこをのぞき込む子ども達のまなざしもメンコイ(*^_^*)トンボ採りから様々な事を学んでいます。
最初の段階で、『すぐ逃がしてあげなさい!』と言っていたら、こんな展開にはならなかったでしょうね。今回は子どもの気持ちが日に日に変化していき、想いや経験を積んだからこそ、子ども達自らどうしたいか提案し合えたのでしょう。遊びや活動を自ら発展させることで、能動的な学びとなる・・・これが保育の醍醐味ですね。
周りの大人の対応としては取った虫をどうするか話し合う事も必要ですよね。“小さな命” を通して、どんな子に育ってほしいかと想いを込めて、子どもに伝えてみるのも良いかと思います。
これから子ども達は社会のルールや守らなければならない事などにたくさん出会うでしょう。今回のように少数派の立場や気持ちを自分が経験することで、相手の気持ちに立って物事を考えられる子になってくれたらな・・など様々な願いを込めて保育すると、子ども達はこんなに素敵な姿を見せてくれます。だから“保育”って面白い!
何度も逃げられた経験を積んで自分流にコツをつかみ、五感をフルに働かせ、からだ全体をとんぼへ集中させ、捕まえた時の達成感!!「よっ!トンボ採り名人!」なんておだてられるともう口元がゆるんでしまって、この上なく嬉しそうな表情に変わります(*’ω’*)(著:園長)
『大切なことは目に見えないからね』~未来の子ども達へとつながっていく~
2018-09-01
ある日のこと・・・しゃがんで泣いているA君と、その傍にただ立ち尽くしているB君が遠くに見えました。

次第に子ども達が年長の二人を取り囲み
「どうしたの?」「B、何かしたの?」「かわいそう」「先生、呼んでこよう」など騒ぎが広がってきていました。
声をかけると、A君は泣いているため話すことが難しいようで、B君は気まずそうな表情をしながらも、ぽつりぽつりと話し始めました。
B君 「床に長いブロックがあったから使ったらA君が返してって言ってきた・・。最初に使ったのは僕だったのに。」次に、お水を飲んで少し気持ちが落ち着いてきたA君に話を聴くと、
A君 「最初に、長いブロック見つけたのはAで、他のブロック取りに行ったらBが使ってたんだ。」二人とも「最初」というキーワードを強調しています。
二人の目は私に向かい、どんな言葉がでてくるのか真剣な表情で待っています。
そこで、私はここに至るまでを振り返り、状況の確認をしました。
すると、さすがは年長さん。
B君は「A君使ってるのはわからなかった・・ごめん。」
それを聞いたA君は「そのまま、置いていっちゃったからな・・。時計の針が○○になったら貸す!」
と互いに相手の思いを想像し、折り合いを付け、自分達で解決が出来ていました。
もちろん、いつもこのように上手くまとまるわけではありません。
しかし、一人ずつ思いをじっくりと聞いて、互いの気持ちを知るきっかけを作ることはとても大切です。納得はできなくても、相手がどう感じて、どう思っていたかを知る体験を重ねる中で次第に思いやりや自制心が育まれていくのだと思います。また、話を聴いてみないと分からないことはよくあるので、ぱっと見えただけの判断で決めつけないようにしています。
一見、好ましくないように見えることにも、そのような行動をとらざるを得なかった理由が隠されているかもしれません。小さい頃からの人との関わり方が人間関係の基盤となるのですから、私達大人はしっかりと思いを聴いて、ハートで見て、その時の最善だと感じる対応を心がけたいですね。 (著:江良)
サン=テグジュペリ 『星の王子さま』
それでは、大事な秘密を教えてあげよう。
とても簡単なことさ。
それはね、ものごとはハートで見なくちゃいけない、っていうことなんだ。
大切なことは、目に見えないからね
引用:『星の王子さま』(ゴマブックス株式会社)
個人面談 ~ 共有しあえる場に・・ ~
2018-08-01
今月は全ご家庭を対象に個人面談を予定しています。
子ども達が園で、どのような場面で頑張っているのかをお伝えしたり、今後どういった関わりが成長へ結びつくのかなどをお伝えしたいと思っています。
また、ご家庭ではどんなことに気を付けて子どもに伝えているかなど伺いながら、双方で子どもの姿を重ね、より子どもを理解していけたらと思っていますので、面談へのご協力を宜しくおねがいいたします。
お子さんの普段のお家での様子は、もちろん誰よりもご存じと思いますが、園での集団生活の様子は、なかなか見えてこない部分でもありますよね。毎年、各クラスにより面談の内容が違い、主に話の中心となるのは・・・
0.1歳児さんは・・・卒乳のタイミング・トイレトレーニング法・離乳食の与え方など
2歳児さんは・・・オムツ外しのタイミング・食事時のお約束・生活リズムの習慣づけ
3歳児さんは・・・お友達との関わり・挨拶の習得・自我を通そうとすること
4・5歳児さんは・・・生活面の自立・活動への集中・自己表現の仕方・情緒面・社会性など
やはり、各年齢によって発達の課題が変わってくるので、お話しさせていただく内容も違ってきます。
子育てにゴールはないのかと思う程、次から次に親の悩みはつきませんが、それと同時に“成長”というご褒美も得ることが出来ますよね。
送迎時に聞こえてくる、保育者と保護者さんとの日々の子どもの成長を伝えあう声。
「オシッコ初めて出せたんですよ!」
「みんなの前で堂々と発表できましたよ」
「泣いている子に優しくしてくれたんです!」etc・・・
このように、子どもの日々の“成長”を保護者の方と共有し合えることは、私たち保育者にとって、とても嬉しい事です。
また、子育ての悩みについても、保護者のみなさんと一緒に考え共有することで少しでも心の重みが軽減できるような存在でありたいと常に思っています。
今月の個人面談で子育てを共有し合う場が広がっていけるといいなと思います(*’ω’*)
著:園長
【きもちを伝える ~ きもちが伝わる嬉しさ】
2018-07-02
ある日の朝…つばめ組の部屋に入ると数人の子が私の指をつかんで
Aくん 「せんせ!ペンギン ごはん あげいこっ!」
Bちゃん 「おべんと、もっていこ!」
Aくん 「こっち、こっち」と、つもり遊び(そこにペンギンさんがいるつもりでの想像遊び)が始まりました。
私も子どもの世界に入り込み
保 「ペンギンさん おなかすいたって。何が食べたいのかなぁ。」
Aくん 「おさかな!」
保 「おさかなかぁ」
と言いながらおさかなに見立てたのか青いブロックを手に取り、そこにいる(であろう)ペンギンさんに食べさせると
Bちゃん 「おいしいって♪」
Cさん 「きりんさん いこ!」
・・・・と世界がどんどん広がっていきました。
このように自分の思いを発信して遊びが始まったり、保育者や友達と同じようなイメージを共有したりしながら
遊びが発展する楽しさを体験していくことで、『気持ちを伝えてそれが伝わる嬉しさ、心地よさ』や
『友達とかかわることの楽しさ』を感覚的に持ってくれたらいいなぁと思います。
それらの積み重ねが友達とかかわっていく時に大切となる『折り合いをつける力』へとつながっていきます。
実は、言葉を話す前から気持ちを伝える心地よさや伝わる嬉しさは、育まれています。
例えば…部屋の窓から外をジーっとみているDちゃん。しゃがみこんで同じ目線で見ると網戸に小さな虫がくっついて
いました。 私が 「 む し だね。」 と虫を指さしながらDちゃんを見るとDちゃんも目線をこちらに向けて
少し目を大きく開いて、虫を指さしました。 この時、言葉は発していなくてもDちゃんと気持ちが通じた気がして
私はすごく嬉しくなりました。
一見何気ない、日常の何てことない一場面ですが、このような些細なやりとりを幾つも幾つも積み重ねていくことが
こども達の未来へとつながっていくのだと思います。
忙しい毎日に流されそうになりながらも、ちょっとした一コマで大切なことを思い出した朝でした。
(著:江良)
~ アクティブ・ラーニングって ~
2018-06-01
園庭に新しい滑り台が出来たので、子ども達はどんどん遊んでいます・・・が、年長さんの数名だけ滑り台の下にもぐり穴を掘り始めていました。あれれ??なにかあるのかな?と様子を伺っていると、土を掘り起こしゴロゴロとした石ころを大量に拾いあさっていました。(おぉ~(;・∀・)それは滑り台の土台を支えるために埋めた石なんだよ~)と焦り“滑り台の下の土は掘らないでね”とお願いしました。しかし、年長さんの言い分としては、ここから掘った石がままごと遊びに丁度良くたくさん掘ると、みんなに喜んでもらえるから・・・ということでした。そうか・・ままごと用の石か。
それは必要だねーとお話しし他に石のある場所を伝え納得のいく穴場を見つけてもらいました(^ ^♪
他にも、ダンゴ虫がいそうな木の根元・モグラの穴の場所、たんぽぽの綿毛がたくさん採れる時期、鬼ごっこで見つかってもダッシュすれば逃げきれる隠れ場所etc・・・年長さんは園庭を知りつくし遊び方を攻略しています。“園庭遊び攻略マニュアル本”なんて出してほしいくらいです(*’ω’*)
年長になった5歳児さんは子ども達の・子ども達による・子ども達だけの『こども会議』を開き、園での遊び方や環境・安全のこと・清潔などについて、自ら考えた意見を友達と伝え合い、子ども達が主体となって園づくりをしていくことを目的とし、さまざまな活動に移していきます。
子どもは好きなことや楽しいことは自ら進んで何度でもやりたがりますよね。子どもにとっての遊びは自発的な活動で一番イキイキしている状態なのでそんなときは、脳の働きは活発になり様々なことを学びどんどん吸収します。このように、幼児期に「遊びの中で育つ力」が伸びてくことで、学童期の「学びの基盤」を作っていくそうです。黒板に書かれた文字をノートに写し、じっと話を聞く知識を詰め込む“チョーク・アンド・トーク”がこれまでの主流でしたが、昨今は心と頭を動かす学習。思考を活性化する学習へと教育の伝え方に変化みられ“アクティブ ラーニング”という言葉をよく耳にするようになりました。このアクティブラーニングは、小学校以上の教育で重視されている“三つの柱”を育成するために有効である
と期待が寄せられています。
・「知識・技能」…何を知っているか、何ができるか
・「思考力・判断力・表現力」…知っている事できる事をどう使うか
・「主体的に学習に取り組む態度」…学びに向かう力、人間性
この中でも「思考力・判断力・表現力」の育成は知識として教えられて習得できるものではなく、それらを経験する場面や想いを積み重ねることで磨かれていく為、実生活で幼児期からたくさん遊び込む経験はとっても大切なのだと思います。
「丸まったダンゴ虫って20数えたらこっそり逃げていくんだよ」「恐竜の体って犬が噛んでも血が出ないんだよ」
「モグラって目があんまり見えてないんだよ」「たんぽぽの綿毛って誰にも見つからないば、頭だけ残るんだね」
子どもたちの声に耳を傾けると、毎日たくさんの発見や好奇心から、想像力を刺激していることが伝わってきますね(*’ω’*)
(著:園長)
~ 子どもの健やかなそだちの応援隊 ~
2018-05-01
新年度が始まり,1か月が経ちました。
初めての環境に戸惑ったり不安を感じていたりした子ども達も,こども園が安心して過ごせる場所ということや大好きな家族がちゃんとお迎えに来てくれることがわかり,笑顔の時間が増えているように思います。また,自分の要求を表現したり,行動範囲を広げるなど,嬉しい変化も見られています。
保護者の皆様にとりましても,園に送った後で『泣いていたけど、大丈夫かな…』『すぐに玩具に走り寄っていたけれど,今頃寂しくなっていないかな‥』と少し不安になったり, お迎え時に保育者に抱っこされてニコニコ笑う姿や,お友だちや保育者と一緒になって遊ぶ姿を見てホッと安堵したりと様々な感情が巡った1か月となったのではないでしょうか。
少しでも保護者の皆様が安心できるように,園での子どもたちの様子を玄関前掲示板やクラス前掲示板,HP,お迎え時に口頭で・・等々いろいろな方法でお伝えしたいと思います。保護者の皆様もご家庭での様子などを教えていただけると嬉しく思います。
このように家庭と園とが相互に子どもの姿を話し合うことで同じ姿に共感したり意外な姿に驚いたりと新たな一面に気づくこともあります。
また,市で行っている健診(つがる市では1歳6か月児・3歳児ならびに5歳児発達相談)においても身体のこと,生活のこと,行動面や言語面など様々な視点から子どものそだちを確認したり,お医者さんや保健師さんに普段気になっていることを相談できる機会があります。その際,家庭での様子に園での様子も加えてお話しすることで多面的な姿を伝えられることと思います。健診前にぜひクラス担任に訪ねてみてくださいね。
もちろん,健診前後に限らず送迎時やお帳面,電話,子育て支援mego megoなどもご活用ください。子ども達と毎日関わる機会をいただいている保育者だからこそお手伝いできることがあるかもしれません。
私たち保育者は‘子どもの健やかなそだち’を保護者の皆様と共に応援し時に悩み,励まし,その一歩一歩を喜び合える存在でありたいと願っています。
『子どもの心に寄り添い、保育の輪を広げます』
という銀杏ヶ丘こども園の保育理念の下に,家庭と園,地域と共に子育ての楽しさが共有できるような機会や環境作りに努めてまいります。
(著:江良)
~ よろしくおねがいします ~
2018-04-02
私達保育者は日頃から、子ども達が安心して遊べる環境作りに取り組み、子ども達がのびのびと毎日を過ごせるような保育を心がけています。また、ご家庭と園とが相互に日常の様子や子どもへの思いや願いなど、伝え合いながら子どもの健やかな成長を共に喜び、共に悩みあえる存在でありたいと思っています。
すくすく通信は7年目を迎えました。日常の子どもの姿から見える『そだち』や『気づき』、『子どもに関する様々なこと』を今後も掲載していくと共に、送迎時や掲示板、連絡帳等でも保育の様子を解りやすくお伝えし、保護者さんとの信頼関係をしっかり築き、深め、連携を取っていきたいと願っています。
保護者の皆様も、日頃の 子育てに対する思いや相談事などございましたら、気軽にお声を掛けてくださいね(*^_^*)
また、子育て支援mego mego や子育て相談など、園内での取り組みへのご参加もお待ちしております。
今後もご協力いただく場面が多々あるかと思いますが、宜しくお願い致します。